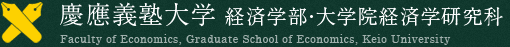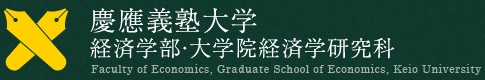AI時代にこそ学ぶべき経済学の価値

慶應義塾大学大学院経済学研究科は2026年で創設から120年を迎えます。1890年の大学部理財科設置から数えると136年にわたり、慶應義塾は我が国の高度な経済学教育を先導してきました。創立者福澤諭吉は義塾の目的を「社会における先導者を育成すること」としておりますが、実際に大学院経済学研究科での学びを基に多くの有為な人材が学界、官界あるいは実業界の先導者として活躍してきました。
さて、昨今の人工知能技術の進展は著しいものがあり、特にここ数年生成AIを使ったサービスが様々な業務にまで利用されており、「人にしかできないこととは」といったAIと職に関する研究も多く行われております。これらの研究からは、比較的単純かつ単調な作業がAIに代替されるのみならず、一定の意思決定が求められる職においてもAI代替が進むという議論もあります。すでに米国を中心にコンピューターサイエンス関連分野での学位取得者の失業率が高まるなど、プログラマーやデータサイエンティストの一部など数年前まで高度と考えられ給与水準が高い職種すらもAIが代替し始めているようです。もちろん世界的に教育研究機関に求められる役割も今後変わっていくでしょう。
しかし、私はこのような時代であるからこそ、経済学を学ぶこと、あるいは経済学研究を行うことの価値がさらに高まると考えます。
経済学は「人・モノ・金・資源・情報など希少な資源がどのように分配されているか」を探る実証科学的側面と、「どのように分配するべきか」に解を与える規範学的側面の両方を持つ稀有な学問体系です。一方、これらの資源を生み出し、あるいは利用する現実の人々や企業の行動は極めて複雑であり、自己の利益や目的のために状況や他者の行動を先読みして行動しています。実際、古くはリーマンショック、最近ですとコロナ禍での世界各国の金融財政政策の変更の前後などでも、人々や企業はこれまでとは異なる行動をとったことがわかっており、過去データだけを利用した予測がことごとく失敗した例は枚挙にいとまがありません。
現状のAIはあくまで過去データのパターンを読み、それを用いて出力を行うものです。一方、複雑な現象を抽象化して本質的な要素間のモデリングを行う、データから本来の因果関係を推論する、さらに規範的立場から複数のステークホルダー間の利害を調整する、といったことは困難です。そして、これらこそ高度な経済学が可能とするきわめて価値の高い行為であり、学問体系として他の社会科学分野や政策決定、企業経営の現場に大きな影響力を与えてきた「人にしかできないこと」なのです。
戦前から「三田の理財」、つまり慶應義塾といえば経済と言われてきただけに、本研究科の教員の研究教育能力は国内トップレベルであり、またいわゆる伝統的な経済学として想像される幅を超えた様々な研究分野を専攻する教員が所属しております。英語のみで入学から学位取得まで学べるカリキュラムの提供や、CEMS国際経営学修士(MIM)コースやブランダイス大学とのダブルディグリー・プログラム、経済学研究科独自の交換留学制度など、意欲的な学生には世界への門戸も広く開かれております。
経済学分野の研究者志望の学生はもちろん、AIに代替されない高度な学びを得て民間や政府NPOなど様々な分野で社会の先導者たらんとする学生に対して常に有益で刺激的な研究教育を行えるよう、幣研究科の教員一同で切磋琢磨していきたいと考えております。
経済学研究科委員長 星野 崇宏