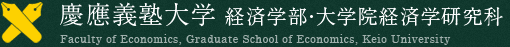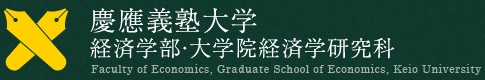A Broadway Age -Women in American Society and Theatrical Culture-
[自発展開型]
加藤千晶(経済学部3年)
指導教員:バティー, ロジャー
要旨
This paper analyzes the position of women on Broadway and how it has changed over time. It examines the history of women‟s theatre before and during the period between 1900 and 1925, when women‟s significance changed greatly. First the introduction will include the history of American public life for women and New York‟s historical background. Next, section two will take up three women who have played an important role in developing Broadway. The women are Mae West, Fanny Brice and Josephine Baker and they will be analyzed each by their original characteristics and features. Section three will look at the role of women as a consumer and audience of the performances on Broadway. Lastly, the conclusion will infer that women started finding their way into American society by arguing their rights on equality. One way for them to carry out their movement was through theatre. When women gained their respect in society, their role models started to change to women on Broadway. When women started to visit Broadway theatres to see these women, the revenues of the theatres and departments stores rose and the golden ages of Broadway began.