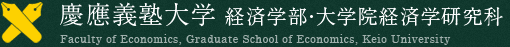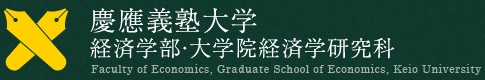教授
藤原 一平
マクロ経済学、国際金融論
経済をシステムとして捉える
研究テーマとその出会い
経済を、時間を通じて変化するシステムとして捉えることに、面白さを感じています。留学した際の修士での専攻はミクロ経済学でしたが、日本銀行にてマクロモデル(経済全体を連立方程式体系として捉えるもの)を担当する部署に着任してから、この研究にのめり込むようになりました。
研究テーマの魅力、面白さ
物事をシンプルに説明することはもちろん大切ですが、一方で、一見単純にみえる現象の裏側には、実は多くの要素が複雑に絡み合っています。
金融政策を例に考えてみましょう。名目金利はインフレ率が上がると上昇するという関係は、直感的に納得しやすいものです。しかし、中央銀行がインフレ率を抑えるために名目金利を引き上げることを考えると、これらは一見矛盾しているようにも感じられます。
実際、短期的には企業が価格を簡単に変更できないため、インフレ率はすぐには変わりません。そのため、中央銀行が政策金利を引き上げると、実質金利が上昇し、消費や投資が減少します。この結果、インフレ率は徐々に低下していくのです。
このように、金融政策の影響を理解するためには、時間を通じた変化と、他の経済主体の行動を考慮に入れる必要があります。システム全体として経済を捉えることで、予想外のメカニズムが働いていることが理解できる点に魅力を感じており、その探求に情熱を注いでいます。
物事をシンプルに説明することはもちろん大切ですが、一方で、一見単純にみえる現象の裏側には、実は多くの要素が複雑に絡み合っています。
金融政策を例に考えてみましょう。名目金利はインフレ率が上がると上昇するという関係は、直感的に納得しやすいものです。しかし、中央銀行がインフレ率を抑えるために名目金利を引き上げることを考えると、これらは一見矛盾しているようにも感じられます。
実際、短期的には企業が価格を簡単に変更できないため、インフレ率はすぐには変わりません。そのため、中央銀行が政策金利を引き上げると、実質金利が上昇し、消費や投資が減少します。この結果、インフレ率は徐々に低下していくのです。
このように、金融政策の影響を理解するためには、時間を通じた変化と、他の経済主体の行動を考慮に入れる必要があります。システム全体として経済を捉えることで、予想外のメカニズムが働いていることが理解できる点に魅力を感じており、その探求に情熱を注いでいます。
学生へのメッセージ
幅広く様々なことに思いを巡らせることと、一つのことを深く掘り下げることは似ていると思っています。なにか共通するメカニズムのようなものを見出すことができ、現象を理解できるような気がします。一方で、そのメカニズムの背景には、様々な事象が複雑に絡み合っており、簡単には説明できないことにも気付かされます。
わかりやすく説明することを試みながらも、その背景は極めて複雑で簡単には説明できないということに、いつも直面しています。矛盾するようですが、ここに、研究の一番の醍醐味があると思っています。
プロフィール

1993年 |
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業 |
1993年 |
日本銀行入行 |
2000年 |
オックスフォード大学経済学研究科修士課程修了 |
2005年 |
大阪大学経済学研究科博士課程修了 応用経済学博士 |
2010年 |
オックスフォード大学経済学研究科博士課程修了 D.Phil. in Economics |
日本銀行、オーストラリア国立大学教授を経て2014年より現職 |
|