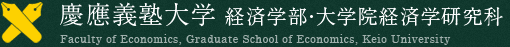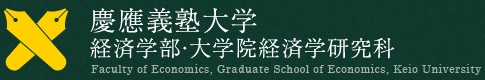教授
中山 純
テキスト言語学、ドイツ語教育、会議通訳者養成教育
変化の時代を過ごして
教員生活を始めた1980年代は、大学教育の大綱化が進められ、一般教育課程が廃止され、教養課程の柱の1つであった外国語教育も大きな変化の波に晒されていきました。大学における外国語教育は教養を念頭に置くべきなのか、それとも実用を重視すべきなのかということが議論されていた時代です。その後、社会の変化や国際化に対応するべく、読解中心の授業から運用面に力点を置いた授業に変質してきたことは改めて言うまでもありません。
経済学部の専任教員になる前に、1981年から数年間、法学部と経済学部でドイツ語を教えていましたが、経済学部の当時のドイツ語クラスには、1クラス50数名もいました。1995年に戻ってきたときは、すでに30名前後に減っていて、現在はさらに小規模なサイズになっています。選択できる語種が増えたこともありますが、学ぶことができる外国語に対する期待と、ドイツ語に対するイメージのミスマッチも学習者が減っている一因かもしれません。
私が初めてドイツ語に触れたのは1960年のことです。それから半世紀以上、この言葉と関わってきましたが、主なドイツ語圏であるドイツやオーストリアも大きな変化を経験してきました。ご存知のようにドイツは1989年から90年にかけて東西に分断されていた状態から再び一つの国になり、永世中立国だったオーストリアはEUに加盟しました。
最近の20数年の、このようなドイツ語圏の変化を、ドイツ語を通してもっと多角的に伝えることができれば、ドイツ語に対する期待にも少しは変化が現れるかもしれません。経済学部の学生には、これからも意欲的にいろいろな言語を学び、多様な視座から社会を捉え、変化を分析しながら進むべき道筋を見極めて、先頭に立って歩んでいく人になって欲しいと願っています。
(2016年1月取材)
プロフィール

1977年 |
学習院大学人文科学研究科ドイツ文学専攻修士課程修了 |
1980年 |
ビーレフェルト大学言語文学部博士課程単位取得退学 |
1981年 |
明治学院大学専任講師 |
1995年 |
経済学部教授 |
※プロフィール・職位は取材当時のものです |
|