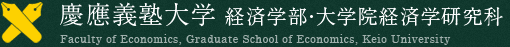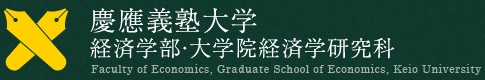教授
大西 広
数理マルクス経済学
数理マルクス経済学にとっての良好な環境
経済学部での教員生活の思い出について
私は最初の赴任先では近代経済学の原論を、2度目の赴任先では統計学を、そして、最後の慶應義塾経済学部ではマルクス経済学の原論を担当しました。ので、大変重要な科目ばかりを順々に担当しましたが、やはり自分が最もやりたかったのは最後のマル経原論です。統計学や近代経済学を過去にやっていましたから、その「マル経原論」も非常に数理的なものとなりましたが、その点で慶應義塾経済学部に感謝したいのは、数学重視の学部入試で入学する学生が過半を占めていることでした。よく言われるように、彼らには「地歴に弱い」という弱点がありつつも、やはりこの混迷した社会に生きている以上、現実問題への強い関心はあります。ので、それを基礎に多くの優秀な学生が私の周りに集まってくれました。これは本当にありがたいことでした。
彼らが大学院に入学し、私の進めるいくつかの研究プロジェクトを引き継いでくれたことも嬉しいことでした。留学生としてドクター・コースに入ってきてくれたLさんは、マルクス派最適成長モデルを使って中国や韓国のマクロ経済の現状評価と予測を行ない、私が中国経済について行った長期予測の修正をしてくれました。より説得力があり、現実的な予測となったと思っています。また、別のY君はこのマルクス派最適成長モデルを前資本制社会の歴史分析に応用し、この研究の一部はG君によって現代の産業を対象とした経営規模格差の変動分析に拡張されています。
私の慶應での後半期の研究は、このマルクス派最適成長モデルから「労働価値説の証明」と「マルクス派数理政治経済学」へと移行しますが、それらの研究でも院生諸君には大いにお世話になりました。先のY君はこの両方の研究で重要な貢献をしてくれましたが、彼に限らず、K君やN君も所得再分配政策と政権交代に関する研究や移民政策をめぐる階級間の利害対抗に関する研究で貢献をしてくれました。今度修士に入学するW君は今、官僚制度の数理モデルをマルクス主義的な立場から構築しようとしています。彼らのうちの多くはまだ大学院に在籍しますので、是非、「数理マルクス」が指導可能なスタッフを雇用し、育てていただければと希望します。
なお、こうして私の慶應経済での研究はマルクス経済学の数理化に関する研究を中心に進みましたので、慶應経済のこれまでの伝統的なマルクス経済学の正反対の研究であると誤解されていますが、実はそうでもありません。井村喜代子先生の経済学は2部門に分割された再生産表式を基礎としたものであって私のモデルも2部門であることに決定的な重要性を持たせたものです。また、北原勇先生の独占価格論も常盤政治先生の地代論も印象に反してかなり「数理的」なものでした。この点は是非皆さんにご理解いただきたいと思います。
いずれにしても皆様、お世話になりました。この場を借りて深くお礼申し上げます。
(2022年1月取材)
プロフィール

1980年 |
京都大学経済学部卒業 |
1982 |
京都大学大学院経済学研究科修士課程修了 |
1985 |
京都大学大学院経済学研究科博士後期課程学修・退学 |
1991 |
経済学博士(京都大学)取得 |
立命館大学経済学部助教授、京都大学経済学部/経済学研究科助教授、教授を経て2012年より現職 |
|
※プロフィール・職位は取材当時のものです |
|