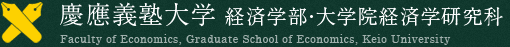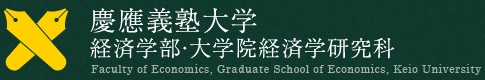教授
池田 幸弘
経済思想史
経済学の王道ではなく
研究者として
1989年に助手として奉職し、爾来三十六年にわたり、経済学部の教員として勤めてまいりました。元来、経済とか経済学とかが好きな生徒、学生ではなく、学部の選択もいやいや感がぬぐえなかったのですが、一泊の宿が一か月に、さらに一年に、そしてこの年月がたったという実感です。そういう学生でしたので、経済学の王道みたいな分野は、避けてきました。三年になって研究会を選ぶ段取りになりましたが、ミクロ経済学とかマクロ経済学とか、あるいは統計、政策のゼミなどは輝きすぎていて、選択の対象からはさっさと外していました。経済史も面白そうでしたが、結果としては経済思想史という分野を選んで、いまに至っています。研究対象としては、カール・メンガーというオーストリアの学者を選びました。ジェボンズやワルラスに比べると資料的な整備が立ち遅れていて、まだ介入の余地がありそうに見えたこともあります。旧制度の助手として採用されてからは、アメリカのデューク大学に寄贈されたメンガー文書を読みに行く機会もえました。その後、ドイツに留学して、メンガーの『国民経済学原理』の成立、というタイトルで学位論文を書き、経済学博士号を取得しました。メンガーはいまでも私のなかでは重要な研究テーマであり続けています。
その後、メンガー伝を書くというライフ・ワークに従事しましたが、いまに至るまで完成していません。若い時は感じませんでしたが、アーカイブ・ワークというものが体力、気力を要することが痛感され、自分にはもうそれを完成させるだけの年数は残されていないのだと感じています。大変残念なことですが、集めた資料を若い研究者と共有して、どこかで研究を託すことになるのかもしれません。
ドイツ留学の考えてもみなかった成果として、日本にたいする関心があります。誰でも経験することではありますが、私は自国についてあまりに無知であることを深く恥じました。その後、これも偶然によるものですが、小泉信三の日記を拝読する機会に恵まれ、その脚注作成にも貢献しました。小泉のイギリス滞在、ドイツ滞在はきわめて面白く、ここから自分の研究との新しい接点も生まれてきました。
教育や行政のこと
残された字数で、教育や行政についてもすこし記してみます。経済学部では、パール・プログラムを導入し、私の担当科目も、ここ十年くらいは英語開講になりました。たんに教授する言語が変わったというだけではなく、いくつかの新しい経験もいしました。さまざまな国と地域からやってきた学生たち。日本人として、さまざまな海外での経験を重ねてきた学生たち。こういう学生を相手に授業をする日々が続きました。母語ではない授業が楽ではなかったことは事実で、いまでも苦労していますが、それでも得られたところは大きかったです。日本語で講義をしていた時期には、履修者はたいてい三桁でしたが、ここのところは数十名で落ち着いています。フィードバックもしていますが、これが正しい講義の在り方なんだと思うに至りました。いままでしていたのは、あれは講義というより講演なんじゃないか。それこそ履修者本位ではなかったのではないかと反省しきりです。
2011年秋からは通信教育部長を拝命、2017年秋からは経済学部長、そして現在は学部の教授と兼任ですが、常任理事として義塾の運営にかかわっております。通信の仕事を請け負っていたさいには、さまざまな学部の方々のご協力をいただきました。公務のかたわら、うかがう他分野の方々のお話にはきわめて興味深いものがありました。これらの役職の役得などはむろん何もありませんが、異分野交流を偶然ながら享受したことは私の財産となっています。さて、残された健康寿命で何をするかですが、退職にあたり、まずは学部や義塾の友人たちに感謝の言葉を申し伝える次第です。
プロフィール

1982年3月 |
慶應義塾大学経済学部卒業 |
1984年3月 |
同大学経済学研究科修士課程修了 |
1989年3月 |
同研究科博士課程単位取得退学 |
1994年7月 |
経済学博士(Dr. oec)をホーエンハイム大学にて取得 |
2004年04月から現在に至る |
慶應義塾大学教授(経済学部) |
2011年10月-2017年9月 |
慶應義塾大学通信教育部長 |
2017年10月-2021年9月 |
慶應義塾大学経済学部長 |
2021年10月から現在に至る |
慶應義塾常任理事(兼務発令) |