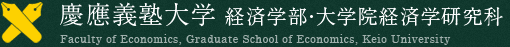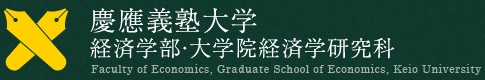教授
嘉治 佐保子
欧州経済、国際マクロ経済学、フィンテック/トークンエコノミー
定年退職にあたって
経済学部での教員生活の思い出について
自分自身はもちろん自分が所属する家族や組織について語るときには謙譲語を使い、誉めない、というのは、日本文化の美しい一面です。しかし最後ですから、少し慶應義塾を誉め自慢ともとれることを言っても、許されるでしょうか。
私と慶應義塾との出会いは1975年に遡ります。米国と日本という大きく異なる二文化の狭間に落ちて悪戦苦闘していた私が、幸いにも慶應義塾女子高等学校に入学できた年です。福澤先生の教えを受け継ぎ個性を肯定する教育環境に恵まれ「水を得た魚」となった私は、前に進み始めることができました。
その三年後に進学し十年後に職を得た経済学部でも、個を尊重し、責任に裏打ちされた自由を認めるという慶應義塾の魂は、脈々と受け継がれていました。「全員に同じ仕事を経験させる」のではなく「その人に合った仕事を任せる」という適材適所の方針は、相対的に得意な仕事をして生産性が高まるので、結局、本人にも組織全体にも有益です。研究面でも、国際経済のゼミ出身でありながら、西洋的合理性と日本的奥ゆかしさを併せ持つ欧州に魅了されて研究に邁進する一方で、やや専門外のフィンテックセンターを立ち上げたときも、多くの同僚教職員に助けられ三田会の皆様からもご支援を得ることができました。 感謝の念にたえません。
定年までの間に日本と世界が経験した様々な変化には良い面と悪い面がありましたが、国を開き多様性を認める方向への変化、そして慶應義塾がその方向を積極的に取り入れたことは、私にとって非常に有難いことでした。とりわけ経済学部PEARLの学生を迎え入れたときには「40年待ってようやく自分と同じ人種に会えた」と感じたものです。「国」と「文化」は違うものであり、どこの国のパスポートを持っていようと同じ文化を共有することはできるのです。
PEARL以前にも、経済学部は3、4年生向けに「すべて英語で学ぶプログラム」 PCP (Professional Career Program)を開始していました。この存在によって容易になったのが、経済学部独自の留学やダブルディグリー制度の設立、CEMSへの参加です。こうして海外の大学との連携を深めたことは、経済学部・経済学研究科そして私自身に、とても良い影響を与えました。教室で聞こえてくる見解は以前と比較にならないほど多様になり、日本で育ち留学予定もない学生にとっても、素晴らしい刺激になっています。
このように、これまで慶應義塾が与えてくれた教育・研究環境は、私にとって最適なものでした。定年退職した後のことについて注文をつけるのは「老害」以外の何物でもありませんが、伝えたいことがあるとしたら、次の三点になります。
第一に、交換留学制度をはじめとする海外の教育・研究機関との関係は、是非、大切にしてほしいと思います。研究教育機関として魅力的であり、その人材が受け入れるに値する水準にあると納得できなくなれば、先方は関係を断ちます。大変残念なことですが、実際にそのような事態に至った例を見たことがあります。「一度結んだ協定は永続する」というわけではないのです。もちろん、努力を怠れば離れてしまうのは、内外の受験生についても言えることです。
第二に、一点目とも関連しますが、日本を取り巻く環境は厳しさを増しています。いわゆる新興国が研究教育につぎ込む金額は財政難に苦しむ日本のそれを大きく上回り、日本企業の国際競争力が相対的に低下すれば各家庭が子供に与えることができる機会、教育にかけることができる資金も減っていくでしょう。日本の目を外に向けさせ、自らを省み改善につなげさせる原資が、少なくとも相対的には低下していくのです。「武士は食わねど高楊枝」ではありませんが、余裕がなくなったとしても理想を低めることなく、工夫を凝らして、知の探求と真の国際人養成を続けてくれることを切に願っています。
第三にAI、とりわけ生成AIについて、慶應義塾のみならず世界レベルの、大きな懸念があります。「AIの利用は人間の可能性を広げる」と言われますが、これは今日の人間の能力水準を前提にした話です。これから先、幼時からずっと生成AIに頼って答えを見つけて育つ子供に、自分の脳で考える能力が身につくでしょうか。「独立自尊」を教育の根幹に据えているのに、AIから独立できていない、AI依存の人間が育つことにならないでしょうか。そして、AI依存の投票者は「民主的に選ばれた」と言いたい独裁者にとって、格好の餌食ではないでしょうか。
前途は多難と言えるかもしれません。しかし、慶應義塾の強みを一つ挙げるとすれば、そのもとに心を一つにして力を合わせる明確な存在があること、つまり福澤先生とその精神があることだと思われます。
私はこれからも、春先には「幻の門近くの早咲きの桜は咲いただろうか」、三田祭のころには「黄金のイチョウは舞っているだろうか」と考えるでしょう。健闘を祈ります。
プロフィール

1982年 |
慶應義塾大学経済学部 卒業 |
1984年 |
慶應義塾大学経済学部 助手 |
1985年から1988年 |
アメリカ合衆国 The Johns Hopkins University 経済学部博士課程に留学 |
1988年から1989年 |
アメリカ合衆国 Yale University 経済学部訪問大学院生 |
1991年 |
慶應義塾大学経済学部 助教授 |
1992年 |
The Johns Hopkins University より Ph.D.(経済学博士号)取得 |
1999年 |
慶應義塾大学経済学部 教授 |
2006年から2023年 |
慶應義塾大学経済学部 Professional Career Programme Co-ordinator 兼務 |
2014年から2023年 |
慶應義塾大学経済学部 PEARL Academic Director 兼務 |
2017年 |
Centre for Finance, Technology and Economics at Keio (FinTEK)を共同設立 |