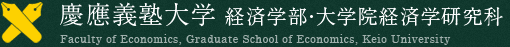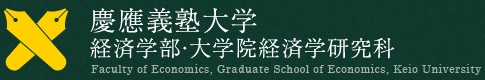教授
七字 眞明
ドイツ文学、ドイツ美術史
「疑うこと」を学ぶ場
経済学部での教員生活の思い出について
哲学者カントは『純粋理性批判』Kritik der reinen Vernunft、『実践理性批判』Kritik der praktischen Vernunft、『判断力批判』Kritik der Urteilskraft、の3編の「批判」の書を著しています。ドイツ語のKritik、英語のcritic、フランス語のcritique、スペイン語のcrítica等の語源を調べればギリシャ語のκριτικήに辿り着きます。元来「よく確かめてみる」という意味を含んだ言葉です。
福澤先生は『学問のすゝめ』第十五編「事物を疑て取捨を断ずる事」において、「信の世界に偽詐多く、疑の世界に真理多し」と記し、「ガリレヲ」、「ガルハニ」、「ニウトン」、「ワット」らは「何れも皆、疑の路に由て真理の奥に達したるものと云うべし」と述べています。
義塾における教育で私は一貫して「まずは疑ってみること」を塾生の皆さんに伝える努力をしてきました。私たちの身の回りの世界は今日、フェイクニュースからステルスマーケットまで、本物を装った偽物で溢れかえっています。「真」と「偽」を見極める力量がますます問われています。その第一歩は、本物であるかどうか「疑うこと」。そして複数の視点から事の正当性を検証してみることです。「人事の進歩して真理に達するの路は、唯異説争論の際にまぎるの一法あるのみ。而してその論説の生ずる源は、疑の一点に在て存するものなり。疑の世界に真理多しとは蓋し是の謂なり」(『学問のすゝめ』)。「疑うことを学ぶ」場としての学府で塾生の一員として仕事を続けてくることができた日々を今、幸せに思い返しています。
プロフィール

1982 |
慶應義塾大学文学部文学科独文学専攻卒業 |
1984年 |
慶應義塾大学院文学研究科独文学専攻修士課程修了 |
1985年 |
DAAD(ドイツ学術交流会)給費奨学生としてドイツ・ケルン大学に留学(1988年帰国) |
1989年 |
慶應義塾大学院文学研究科独文学専攻博士課程単位取得退学 |
1989年 |
慶應義塾大学法学部・総合政策学部・環境情報学部非常勤講師(~1991年) |
1991年 |
慶應義塾大学経済学部助手 |
1993年 |
慶應義塾大学経済学部専任講師 |
1994年 |
慶應義塾大学経済学部助教授 |
2002年 |
慶應義塾大学経済学部教授(~現在) |
2013年 |
東京大学大学院人文社会系研究科・同大学文学部非常勤講師(~2015年) |